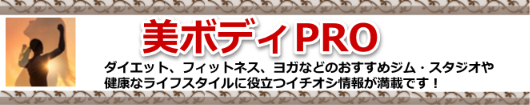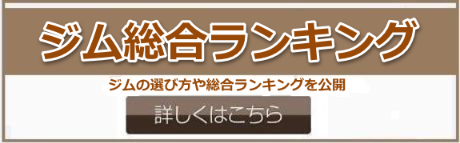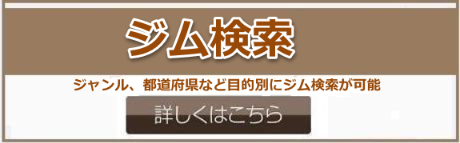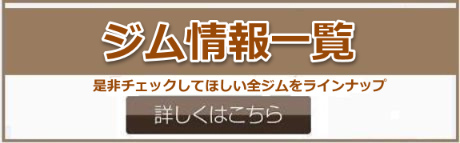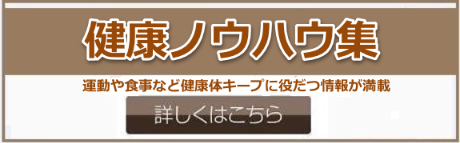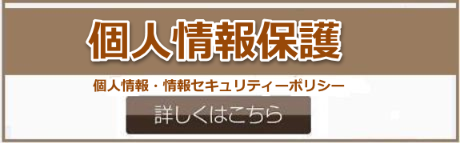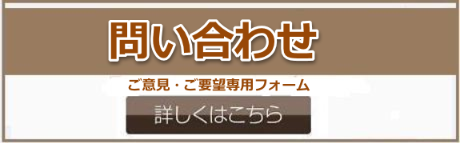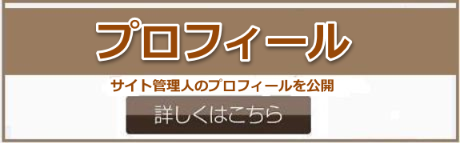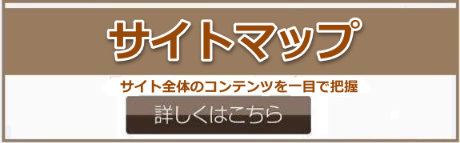座りながらできる運動11選!運動不足解消効果ややり方のコツも解説

座ったままで行える運動に関しては、健康効果の有無や実際の成果について意見が分かれやすいのが現状です。手軽さゆえに注目を集めていますが、「本当に効果があるのか」「運動として十分なのか」と疑問を持つ人も少なくありません。その一方で、体力に自信がない人や長時間立つことが難しい人にとっては、取り入れやすい方法として支持される側面もあります。こうした賛否の声が混在しているからこそ、実際に試したいと感じる人が増えているのです。
そこで以下にその詳細についてまとめてみました。
■必読情報
目次
座りながらできる運動の運動不足解消効果
座りながらできる運動は、体を大きく動かさないため本当に効果があるのか疑問を持つ人も少なくありません。しかし実際には、日常的に座って過ごす時間が長い現代人にとって、十分に運動不足の改善につながる可能性を秘めています。その理由のひとつは「筋肉の刺激」にあります。座った姿勢であっても、足を持ち上げたり、腹筋を意識してひねる動作を取り入れたりすることで、下半身や体幹の筋肉に負荷を与えることができます。筋肉は使わなければ衰えるため、たとえ軽い動きであっても継続的に刺激を与えることが重要なのです。
また、座ったままの運動は血流改善にも効果的です。長時間同じ姿勢で座り続けると、血液が滞って足のむくみや冷えを引き起こすことがあります。そこで、かかとを上げ下げしたり、足首を回したりする運動を行うことで血液循環が促され、体全体の代謝が活発になります。こうした変化は見えにくいですが、日々の体調を支える大切な要素です。
さらに、座りながらの運動は「続けやすさ」においても優れています。立ち上がって運動するスペースが不要であり、仕事中や休憩時間に気軽に取り入れることができるため、運動を習慣化しやすいのです。どんなに効果的な運動であっても継続できなければ意味がありません。その点、座ったままの運動は心理的なハードルが低く、日常に自然と取り入れられるのが強みといえます。
また、座ったままの運動は血流改善にも効果的です。長時間同じ姿勢で座り続けると、血液が滞って足のむくみや冷えを引き起こすことがあります。そこで、かかとを上げ下げしたり、足首を回したりする運動を行うことで血液循環が促され、体全体の代謝が活発になります。こうした変化は見えにくいですが、日々の体調を支える大切な要素です。
さらに、座りながらの運動は「続けやすさ」においても優れています。立ち上がって運動するスペースが不要であり、仕事中や休憩時間に気軽に取り入れることができるため、運動を習慣化しやすいのです。どんなに効果的な運動であっても継続できなければ意味がありません。その点、座ったままの運動は心理的なハードルが低く、日常に自然と取り入れられるのが強みといえます。
座りながらできる運動11選
座りながらできる運動のお勧めを知っておくことは、生活習慣に運動を取り入れるハードルを下げるうえで大切です。立ち上がる余裕がない時でも体を動かせる方法を理解していれば、忙しさや体調の波に左右されず継続できます。結果的に運動不足の改善や健康維持につながるのです。
そこで座りながらできる運動のお勧めについて解説します。
かかと落としと足踏みは、シンプルながらも運動不足の解消に役立つ方法として注目されています。どちらも狭いスペースで行えるため、特別な器具や広い場所を必要とせず、日常の合間に取り入れやすいのが魅力です。特にかかと落としは、かかとを床に軽く打ちつけることで骨や筋肉に適度な刺激を与え、血流を促進しやすくなります。これにより下半身の冷えやむくみを防ぎ、代謝の活性化にもつながるのです。足踏みはリズム良く足を動かすことで全身の血行を高め、軽い有酸素運動の効果を得られる点が強みといえます。
やり方のコツとしては、かかと落としでは背筋を伸ばし、呼吸を止めないように注意しながらリズム良く行うことが大切です。勢いをつけすぎると関節に負担がかかるため、軽快な動きを意識すると安心です。一方の足踏みは、太ももを少し高めに持ち上げることで筋肉への刺激が増し、より運動効果を感じやすくなります。無理をせず、自分のペースで続けられる範囲で行うことが継続の秘訣です。
下半身トレーニングは、運動不足を解消するうえでとても効果的な方法です。なぜなら、太ももやお尻、ふくらはぎといった下半身の筋肉は体の中でも大きな割合を占めており、ここを動かすことで消費エネルギーが増えやすいからです。さらに、下半身の筋肉は血液を心臓へ押し戻すポンプのような役割も担っており、鍛えることで血流がスムーズになり、冷えやむくみの改善にもつながります。こうした理由から、下半身を意識的に動かすことは、体全体の代謝を高める近道といえるのです。
やり方のコツとしては、まず正しいフォームを意識することが大切です。例えばスクワットを行う場合、背中を丸めずに胸を張り、膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。浅い動きから始めて、慣れてきたら少しずつ深くしていくと安全です。また、ランジのように片足を前に出す動作では、バランスを崩さないように腹筋も意識するとより効果的です。
足首の運動は、一見すると小さな動きに思えるかもしれませんが、運動不足の改善に役立つ効果を秘めています。足首は血液を下半身から心臓へ送り返すポンプのような役割を担っており、ここをしっかり動かすことで血流がスムーズになり、むくみや冷えの予防につながります。特に長時間座りっぱなしの生活が続く人にとっては、足首を動かすだけでも全身の循環を助け、代謝の低下を防ぐ効果が期待できるのです。
やり方のコツとしては、まず椅子に座った状態で片足を少し浮かせ、足首をゆっくりと大きく回す方法がおすすめです。内回し・外回しの両方を行うことで関節の可動域を広げる効果があります。また、つま先を上下に動かす運動も取り入れると、ふくらはぎの筋肉が刺激されて血流改善により効果的です。呼吸を止めず、リズムよく行うことが続けやすさのポイントになります。
つま先の運動は、日常の中で簡単に取り入れられる動作でありながら、運動不足の解消に効果を発揮します。つま先を上下に動かすことで、ふくらはぎの筋肉がしっかりと働き、下半身の血流が促進されます。特に長時間のデスクワークや立ち仕事では血液が滞りやすく、むくみやだるさの原因となりますが、つま先を意識的に動かすことでその予防につながるのです。また、ふくらはぎは“第二の心臓”とも呼ばれるほど重要な部位であり、ここを鍛えることで全身の循環機能を支え、基礎代謝の維持にも貢献します。
やり方のコツとしては、椅子に座った状態でかかとを床につけたままつま先を持ち上げ、ゆっくりと下ろす動きを繰り返すのが基本です。リズムを急がず、一回ごとに筋肉が伸び縮みしているのを意識すると効果が高まります。立った状態で行う場合は、かかとを上げてつま先立ちになり、数秒キープしてから下ろす動作を取り入れるとさらに負荷がかかり、下半身強化にもつながります。
座ったままの腹筋運動は、限られたスペースでも取り入れられるシンプルな方法であり、運動不足の解消に役立ちます。特に腹筋は体幹を支える重要な筋肉であり、衰えると姿勢の乱れや腰痛の原因になりやすい部位です。椅子に座ったままでも腹筋を刺激することは十分可能で、継続することで基礎代謝の維持や内臓の位置を安定させる効果が期待できます。さらに、体幹が強化されることで日常の動作がスムーズになり、疲れにくい体づくりにもつながるのです。
やり方のコツとしては、まず背もたれに頼らず椅子に腰掛け、両手を太ももに置いて姿勢を安定させます。その状態でお腹に力を入れながら両膝を軽く持ち上げ、数秒キープしてから下ろす動作を繰り返すのが基本です。呼吸を止めずに動作に合わせて息を吐くことで、より深く腹筋に刺激が入ります。慣れてきたら片足ずつ交互に上げ下げしたり、膝を抱えるようにして体を丸めたりするバリエーションを加えると強度を調整できます。
座ったままの筋トレは、 デスクワークが多い人や 体力に自信がない人や長時間立つのが難しい人でも手軽に取り入れられる運動方法です。椅子に座った状態で腕や脚、腹筋を動かすだけでも筋肉に適度な負荷がかかり、血流の促進や基礎代謝の維持に効果があります。特に普段あまり使わない体幹や下半身の筋肉を刺激することで、姿勢の改善や疲れにくい体づくりにもつながります。無理なく続けられる点から、運動不足を解消するための第一歩として非常に有効です。
やり方のコツとしては、まず背筋を伸ばし、椅子に深く腰掛けて安定した姿勢を作ることが大切です。腕の筋トレでは、ペットボトルや軽いダンベルを持って肘を曲げ伸ばしする動作を行うと負荷がかかります。脚の筋トレでは、膝をゆっくり持ち上げたり、足を前方に伸ばしてキープしたりすることで下半身の筋肉を効果的に使えます。腹筋を意識する場合は、お腹に力を入れながら体を少し前に倒す動作を加えると体幹も鍛えられます。
膝の間にクッションを挟んで押す内転筋運動は、座ったままでも行える下半身トレーニングとして運動不足解消に有効です。内転筋は太ももの内側にある筋肉で、歩行や立ち座りといった日常動作を支える重要な部位です。ここを鍛えることで、脚の安定性が高まり、姿勢の改善や膝関節への負担軽減にもつながります。また、内転筋を刺激することで血流が促され、下半身のむくみやだるさを予防する効果も期待できます。
やり方のコツとしては、椅子に腰掛けた状態で両膝の間に適度な硬さのクッションを挟みます。膝をしっかり閉じるようにクッションを押し、そのまま数秒キープしてから力を抜く動作を繰り返します。呼吸を止めず、押す時にお腹にも軽く力を入れると体幹の安定性も同時に鍛えられます。回数や時間は無理のない範囲から始め、慣れてきたら少しずつキープ時間を延ばすと効果が高まります。
座ったまま行う背中と首のストレッチは、運動不足による筋肉のこわばりや血流の滞りを和らげる効果があります。長時間座って仕事をしたりスマートフォンを操作したりする生活では、背中や首の筋肉が硬くなりやすく、肩こりや頭痛、姿勢の悪化につながることがあります。座った状態で軽く体を伸ばすだけでも筋肉がほぐれ、血流が促されることで代謝や疲労回復のサポートになるのです。また、首や背中の柔軟性が向上することで、日常の動作がスムーズになり、体全体の負担軽減にも役立ちます。
やり方のコツとしては、まず椅子に深く腰掛けて背筋をまっすぐに伸ばします。肩の力を抜き、両手を頭の後ろや太ももに置いて安定させます。首をゆっくり左右に倒したり、前後に傾けたりして筋肉を伸ばす際は、痛みを感じない範囲で行うことが大切です。背中を丸めたり反らせたりする動作も組み合わせると、肩甲骨周りや胸筋の柔軟性も同時に高められます。呼吸を止めず、動作に合わせて深く息を吐くと効果的です。
座ったままの肩甲骨運動は、運動不足で凝り固まった上半身の筋肉をほぐし、血流を促進する効果があります。肩甲骨周りの筋肉は、腕や背中の動きを支える重要な部位であり、ここが硬くなると肩こりや首の張り、姿勢の悪化につながります。座ったままでも肩甲骨を意識的に動かすことで、筋肉に適度な刺激を与え、可動域を広げることができます。さらに、肩甲骨周りの柔軟性が向上すると、日常生活での動作がスムーズになり、全身の血流改善や運動不足の解消にも寄与するのです。
やり方のコツとしては、まず椅子に深く腰掛け、背筋をまっすぐに伸ばして姿勢を安定させます。両肩を軽く上げて耳に近づけるように持ち上げた後、ゆっくりと肩を後ろに回しながら下ろす「肩回し運動」を行います。肩甲骨を意識して寄せるように動かすと、筋肉の収縮を感じやすくなります。また、両腕を前に伸ばして肩甲骨を開閉する動作も取り入れると、さらに可動域が広がり、血流促進効果が高まります。呼吸を止めず、動作をゆっくり行うことが継続のポイントです。
座ったまま手をグーパーと繰り返す運動は、一見簡単な動作ですが、運動不足の解消に意外な効果があります。手や指の筋肉を動かすことで血流が促進され、冷えやむくみの改善に寄与します。また、腕や前腕の筋肉を軽く刺激することで、日常的に使われにくい部分の筋力低下を防ぐことができます。特にデスクワークやスマートフォン操作で固まりやすい手首や指の関節を動かすことで、関節の柔軟性も維持でき、肩や首のこりの軽減にもつながるのです。
やり方のコツとしては、椅子に座った状態で腕を前に伸ばし、手のひらを大きく開いた後、しっかりと握ってグーにします。開くときも握るときも、指先や手のひらに力を意識的に入れることで、筋肉により効果的に刺激が伝わります。呼吸を止めず、リズムよく繰り返すことがポイントです。また、慣れてきたら両手同時だけでなく交互に動かすことで、血流の循環がさらに促され、腕全体の筋肉をバランスよく使うことができます。
手首のストレッチ運動は、運動不足で固まりやすい手首や前腕の筋肉をほぐし、血流を改善する効果があります。長時間のデスクワークやスマートフォン操作では手首の関節や筋肉が緊張しやすく、こわばりやだるさの原因になりやすいです。手首を意識的に動かすことで、関節の可動域を広げ、前腕や肩周りの筋肉にも軽い刺激を与えることができます。これにより、運動不足による血行不良や疲労の蓄積を防ぎ、日常生活での手の動きをスムーズに保つことが可能になります。
やり方のコツとしては、椅子に座った状態で片手を前に伸ばし、もう片方の手で指先や手のひらを軽く引っ張るようにして手首を曲げます。手のひらを上に向けたり下に向けたりして、前腕の筋肉も同時に伸ばすと効果的です。各動作は痛みを感じない範囲で行い、呼吸を止めずにゆっくりと数秒間キープすることがポイントです。慣れてきたら、手首を左右に回す動作も加えると関節の柔軟性がさらに高まります。
かかと落としと足踏み
かかと落としと足踏みは、シンプルながらも運動不足の解消に役立つ方法として注目されています。どちらも狭いスペースで行えるため、特別な器具や広い場所を必要とせず、日常の合間に取り入れやすいのが魅力です。特にかかと落としは、かかとを床に軽く打ちつけることで骨や筋肉に適度な刺激を与え、血流を促進しやすくなります。これにより下半身の冷えやむくみを防ぎ、代謝の活性化にもつながるのです。足踏みはリズム良く足を動かすことで全身の血行を高め、軽い有酸素運動の効果を得られる点が強みといえます。
やり方のコツとしては、かかと落としでは背筋を伸ばし、呼吸を止めないように注意しながらリズム良く行うことが大切です。勢いをつけすぎると関節に負担がかかるため、軽快な動きを意識すると安心です。一方の足踏みは、太ももを少し高めに持ち上げることで筋肉への刺激が増し、より運動効果を感じやすくなります。無理をせず、自分のペースで続けられる範囲で行うことが継続の秘訣です。
下半身トレーニング
下半身トレーニングは、運動不足を解消するうえでとても効果的な方法です。なぜなら、太ももやお尻、ふくらはぎといった下半身の筋肉は体の中でも大きな割合を占めており、ここを動かすことで消費エネルギーが増えやすいからです。さらに、下半身の筋肉は血液を心臓へ押し戻すポンプのような役割も担っており、鍛えることで血流がスムーズになり、冷えやむくみの改善にもつながります。こうした理由から、下半身を意識的に動かすことは、体全体の代謝を高める近道といえるのです。
やり方のコツとしては、まず正しいフォームを意識することが大切です。例えばスクワットを行う場合、背中を丸めずに胸を張り、膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。浅い動きから始めて、慣れてきたら少しずつ深くしていくと安全です。また、ランジのように片足を前に出す動作では、バランスを崩さないように腹筋も意識するとより効果的です。
足首の運動
足首の運動は、一見すると小さな動きに思えるかもしれませんが、運動不足の改善に役立つ効果を秘めています。足首は血液を下半身から心臓へ送り返すポンプのような役割を担っており、ここをしっかり動かすことで血流がスムーズになり、むくみや冷えの予防につながります。特に長時間座りっぱなしの生活が続く人にとっては、足首を動かすだけでも全身の循環を助け、代謝の低下を防ぐ効果が期待できるのです。
やり方のコツとしては、まず椅子に座った状態で片足を少し浮かせ、足首をゆっくりと大きく回す方法がおすすめです。内回し・外回しの両方を行うことで関節の可動域を広げる効果があります。また、つま先を上下に動かす運動も取り入れると、ふくらはぎの筋肉が刺激されて血流改善により効果的です。呼吸を止めず、リズムよく行うことが続けやすさのポイントになります。
つま先の運動
つま先の運動は、日常の中で簡単に取り入れられる動作でありながら、運動不足の解消に効果を発揮します。つま先を上下に動かすことで、ふくらはぎの筋肉がしっかりと働き、下半身の血流が促進されます。特に長時間のデスクワークや立ち仕事では血液が滞りやすく、むくみやだるさの原因となりますが、つま先を意識的に動かすことでその予防につながるのです。また、ふくらはぎは“第二の心臓”とも呼ばれるほど重要な部位であり、ここを鍛えることで全身の循環機能を支え、基礎代謝の維持にも貢献します。
やり方のコツとしては、椅子に座った状態でかかとを床につけたままつま先を持ち上げ、ゆっくりと下ろす動きを繰り返すのが基本です。リズムを急がず、一回ごとに筋肉が伸び縮みしているのを意識すると効果が高まります。立った状態で行う場合は、かかとを上げてつま先立ちになり、数秒キープしてから下ろす動作を取り入れるとさらに負荷がかかり、下半身強化にもつながります。
腹筋運動
座ったままの腹筋運動は、限られたスペースでも取り入れられるシンプルな方法であり、運動不足の解消に役立ちます。特に腹筋は体幹を支える重要な筋肉であり、衰えると姿勢の乱れや腰痛の原因になりやすい部位です。椅子に座ったままでも腹筋を刺激することは十分可能で、継続することで基礎代謝の維持や内臓の位置を安定させる効果が期待できます。さらに、体幹が強化されることで日常の動作がスムーズになり、疲れにくい体づくりにもつながるのです。
やり方のコツとしては、まず背もたれに頼らず椅子に腰掛け、両手を太ももに置いて姿勢を安定させます。その状態でお腹に力を入れながら両膝を軽く持ち上げ、数秒キープしてから下ろす動作を繰り返すのが基本です。呼吸を止めずに動作に合わせて息を吐くことで、より深く腹筋に刺激が入ります。慣れてきたら片足ずつ交互に上げ下げしたり、膝を抱えるようにして体を丸めたりするバリエーションを加えると強度を調整できます。
筋トレ
座ったままの筋トレは、 デスクワークが多い人や 体力に自信がない人や長時間立つのが難しい人でも手軽に取り入れられる運動方法です。椅子に座った状態で腕や脚、腹筋を動かすだけでも筋肉に適度な負荷がかかり、血流の促進や基礎代謝の維持に効果があります。特に普段あまり使わない体幹や下半身の筋肉を刺激することで、姿勢の改善や疲れにくい体づくりにもつながります。無理なく続けられる点から、運動不足を解消するための第一歩として非常に有効です。
やり方のコツとしては、まず背筋を伸ばし、椅子に深く腰掛けて安定した姿勢を作ることが大切です。腕の筋トレでは、ペットボトルや軽いダンベルを持って肘を曲げ伸ばしする動作を行うと負荷がかかります。脚の筋トレでは、膝をゆっくり持ち上げたり、足を前方に伸ばしてキープしたりすることで下半身の筋肉を効果的に使えます。腹筋を意識する場合は、お腹に力を入れながら体を少し前に倒す動作を加えると体幹も鍛えられます。
内転筋運動
膝の間にクッションを挟んで押す内転筋運動は、座ったままでも行える下半身トレーニングとして運動不足解消に有効です。内転筋は太ももの内側にある筋肉で、歩行や立ち座りといった日常動作を支える重要な部位です。ここを鍛えることで、脚の安定性が高まり、姿勢の改善や膝関節への負担軽減にもつながります。また、内転筋を刺激することで血流が促され、下半身のむくみやだるさを予防する効果も期待できます。
やり方のコツとしては、椅子に腰掛けた状態で両膝の間に適度な硬さのクッションを挟みます。膝をしっかり閉じるようにクッションを押し、そのまま数秒キープしてから力を抜く動作を繰り返します。呼吸を止めず、押す時にお腹にも軽く力を入れると体幹の安定性も同時に鍛えられます。回数や時間は無理のない範囲から始め、慣れてきたら少しずつキープ時間を延ばすと効果が高まります。
背中と首のストレッチ
座ったまま行う背中と首のストレッチは、運動不足による筋肉のこわばりや血流の滞りを和らげる効果があります。長時間座って仕事をしたりスマートフォンを操作したりする生活では、背中や首の筋肉が硬くなりやすく、肩こりや頭痛、姿勢の悪化につながることがあります。座った状態で軽く体を伸ばすだけでも筋肉がほぐれ、血流が促されることで代謝や疲労回復のサポートになるのです。また、首や背中の柔軟性が向上することで、日常の動作がスムーズになり、体全体の負担軽減にも役立ちます。
やり方のコツとしては、まず椅子に深く腰掛けて背筋をまっすぐに伸ばします。肩の力を抜き、両手を頭の後ろや太ももに置いて安定させます。首をゆっくり左右に倒したり、前後に傾けたりして筋肉を伸ばす際は、痛みを感じない範囲で行うことが大切です。背中を丸めたり反らせたりする動作も組み合わせると、肩甲骨周りや胸筋の柔軟性も同時に高められます。呼吸を止めず、動作に合わせて深く息を吐くと効果的です。
肩甲骨運動
座ったままの肩甲骨運動は、運動不足で凝り固まった上半身の筋肉をほぐし、血流を促進する効果があります。肩甲骨周りの筋肉は、腕や背中の動きを支える重要な部位であり、ここが硬くなると肩こりや首の張り、姿勢の悪化につながります。座ったままでも肩甲骨を意識的に動かすことで、筋肉に適度な刺激を与え、可動域を広げることができます。さらに、肩甲骨周りの柔軟性が向上すると、日常生活での動作がスムーズになり、全身の血流改善や運動不足の解消にも寄与するのです。
やり方のコツとしては、まず椅子に深く腰掛け、背筋をまっすぐに伸ばして姿勢を安定させます。両肩を軽く上げて耳に近づけるように持ち上げた後、ゆっくりと肩を後ろに回しながら下ろす「肩回し運動」を行います。肩甲骨を意識して寄せるように動かすと、筋肉の収縮を感じやすくなります。また、両腕を前に伸ばして肩甲骨を開閉する動作も取り入れると、さらに可動域が広がり、血流促進効果が高まります。呼吸を止めず、動作をゆっくり行うことが継続のポイントです。
手をグーパー繰り返し
座ったまま手をグーパーと繰り返す運動は、一見簡単な動作ですが、運動不足の解消に意外な効果があります。手や指の筋肉を動かすことで血流が促進され、冷えやむくみの改善に寄与します。また、腕や前腕の筋肉を軽く刺激することで、日常的に使われにくい部分の筋力低下を防ぐことができます。特にデスクワークやスマートフォン操作で固まりやすい手首や指の関節を動かすことで、関節の柔軟性も維持でき、肩や首のこりの軽減にもつながるのです。
やり方のコツとしては、椅子に座った状態で腕を前に伸ばし、手のひらを大きく開いた後、しっかりと握ってグーにします。開くときも握るときも、指先や手のひらに力を意識的に入れることで、筋肉により効果的に刺激が伝わります。呼吸を止めず、リズムよく繰り返すことがポイントです。また、慣れてきたら両手同時だけでなく交互に動かすことで、血流の循環がさらに促され、腕全体の筋肉をバランスよく使うことができます。
手首のストレッチ
手首のストレッチ運動は、運動不足で固まりやすい手首や前腕の筋肉をほぐし、血流を改善する効果があります。長時間のデスクワークやスマートフォン操作では手首の関節や筋肉が緊張しやすく、こわばりやだるさの原因になりやすいです。手首を意識的に動かすことで、関節の可動域を広げ、前腕や肩周りの筋肉にも軽い刺激を与えることができます。これにより、運動不足による血行不良や疲労の蓄積を防ぎ、日常生活での手の動きをスムーズに保つことが可能になります。
やり方のコツとしては、椅子に座った状態で片手を前に伸ばし、もう片方の手で指先や手のひらを軽く引っ張るようにして手首を曲げます。手のひらを上に向けたり下に向けたりして、前腕の筋肉も同時に伸ばすと効果的です。各動作は痛みを感じない範囲で行い、呼吸を止めずにゆっくりと数秒間キープすることがポイントです。慣れてきたら、手首を左右に回す動作も加えると関節の柔軟性がさらに高まります。
■役立つ関連記事
まとめ
今回は
座りながらできる運動
についてのお話でした。
以上の説明がお役に立てたのであれば幸いですが、もし解決に至らないようであれば、 一流トレーナーの運動や食事指導が受けられるジムで 無料カウンセリング又は無料体験レッスンを受けてみてください。
■是非読んでほしい必読情報
以上の説明がお役に立てたのであれば幸いですが、もし解決に至らないようであれば、 一流トレーナーの運動や食事指導が受けられるジムで 無料カウンセリング又は無料体験レッスンを受けてみてください。
■是非読んでほしい必読情報