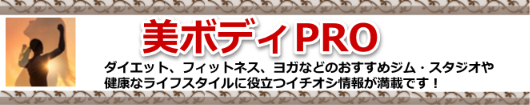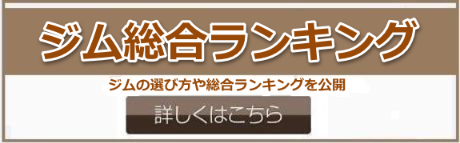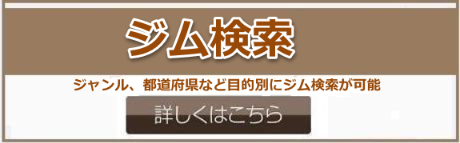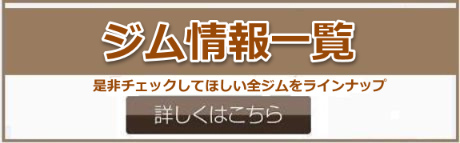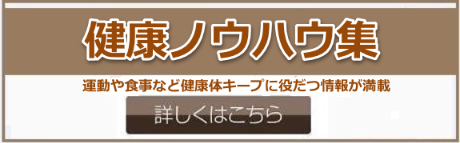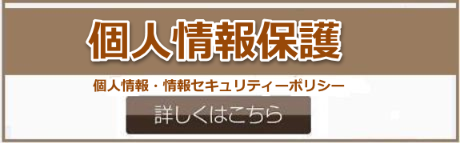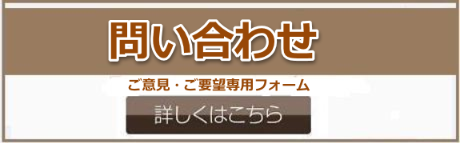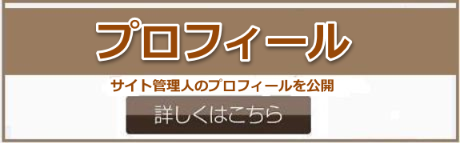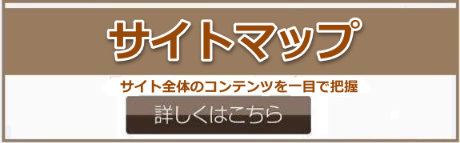自転車の運動不足解消効果14選!やり方やランキングも公開

自転車・ママチャリの運動不足解消効果については、意見が分かれることが多く、どの情報を信じればよいのか迷う人も少なくありません。軽いサイクリングでも下半身の筋肉を使い、心肺機能の向上や脂肪燃焼に寄与すると言われる一方で、短時間の走行や平坦な道だけでは十分な運動にならないとの指摘もあります。このため、効果を実感するには距離や強度を工夫し、自分の体力や目的に合わせて継続することが重要です。
そこで以下にその詳細についてまとめてみました。
■必読情報
目次
- 1 自転車運動とは?
- 2 自転車の運動不足解消効果14選
- 3 自転車運動のやり方のコツ20選
- 3.1 サドルの高さを自分の足に合った位置に調整する
- 3.2 ハンドルの高さを無理なく握れる位置に設定する
- 3.3 ペダルを回す際はつま先でなく足全体を使う
- 3.4 背筋をまっすぐに保ち、猫背にならないよう意識する
- 3.5 肩の力を抜き、リラックスした姿勢で漕ぐ
- 3.6 呼吸は止めず、自然なリズムで行う
- 3.7 ペダルの回転は一定のリズムを保ち、急に速くしない
- 3.8 適度な負荷をかけて心拍数を上げる
- 3.9 長時間漕ぐ場合は途中で休憩を挟む
- 3.10 水分補給を適宜行う
- 3.11 路面や交通状況に注意し、安全第一で走る
- 3.12 運動前に軽いウォームアップ、運動後にクールダウンを行う
- 3.13 屋外では天候に応じて服装を調整する
- 3.14 集団で走る場合は周囲との距離を意識する
- 3.15 定期的にスピードや距離を少しずつ増やす
- 3.16 自分の体調や疲労度に応じて運動時間を調整する
- 3.17 音楽や景色などでモチベーションを保つ
- 3.18 無理せず、体に痛みや違和感があれば中止する
- 3.19 ペダルを漕ぐ際はリズムよく、片足だけで力を入れすぎない
- 3.20 週に何度か定期的に行い、習慣化する
- 4 自転車のランキングをチェック
- 5 まとめ
自転車運動とは?
自転車運動は、ペダルを漕ぐ動作を中心とした有酸素運動で、下半身の筋肉を効率的に鍛えることができる点が特徴です。太ももやふくらはぎ、臀部の筋肉を使うことで、日常生活では使いにくい筋肉も刺激され、筋力アップや基礎代謝の向上につながります。また、有酸素運動として心肺機能を高める効果もあり、血流の改善や脂肪燃焼に役立つため、健康維持や体力向上を目指す人にも適しています。
自転車運動は、屋外でのサイクリングや室内でのエアロバイクなど、環境に合わせて選べる柔軟性も魅力です。屋外では景色を楽しみながらリフレッシュでき、室内では天候に左右されず安全に運動を行えます。さらに、膝や腰への負担が少ないため、ジョギングなどに比べて関節に優しく、怪我のリスクを抑えながら継続できる運動です。
自転車運動は、有酸素運動として心肺機能を高めると同時に、下半身の筋力を効率よく鍛えることができるバランスの良い運動です。無理なく体を動かし、健康維持や体力向上を目指すための手段として、多くの人に取り入れやすい運動と言えます。
自転車の運動不足解消効果14選
自転車の運動不足解消効果を理解しておくことは、効率的に健康や体力を維持するために重要です。ペダルを漕ぐ動作で下半身の筋力や心肺機能を鍛えられる一方、無理な距離や強度では効果が薄れることもあります。自分の体力や目的に合わせて運動計画を立てるために、効果の仕組みを知ることは欠かせません。
そこで自転車の運動不足解消効果について解説します。
さらに、定期的に自転車を漕すことで血管の弾力性が維持され、高血圧の予防や循環器系の健康促進にも役立ちます。
さらに、自転車運動は負荷を調整しやすく、自分の体力や体調に合わせてペースや距離をコントロールできる点も魅力です。
また、無理のない強度で継続して自転車を漕ぐことで、基礎代謝の向上が段階的に実感できる点も魅力です。
下半身の筋力強化
ペダルを漕ぐ動作では、太ももやふくらはぎ、臀部の筋肉が自然に使われ、日常生活では鍛えにくい筋肉も刺激されます。これにより、脚力が向上するだけでなく、基礎代謝の向上や体の安定性にもつながります。また、膝や腰にかかる負担が少ないため、ランニングやジャンプ系の運動が苦手な人でも安全に下半身を鍛えることが可能です。心肺機能の向上
ペダルを一定のリズムで漕ぎ続けることで、心臓の拍動や呼吸が活発になり、酸素を体全体に効率よく運ぶ能力が向上します。これにより、日常生活での疲労感が軽減され、体力や持久力も自然と高まります。また、心肺機能の向上は血流や代謝の改善にもつながり、健康維持や生活習慣病の予防にも役立ちます。脂肪燃焼・体重管理
ペダルを漕ぐ動作は持続的な有酸素運動となり、体内の脂肪を効率よくエネルギーとして消費します。特に中強度で長時間走行することで、体脂肪の減少が期待でき、体重管理にも役立ちます。また、下半身の大きな筋肉を使うため、基礎代謝が向上し、安静時でも消費カロリーが増えることから、より効率的に体重コントロールが可能です。血流改善
ペダルを漕ぐことで下半身の筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、血液が心臓へと戻る循環がスムーズになります。これにより、末梢まで血液が行き渡りやすくなり、冷え性やむくみの改善にもつながります。また、全身の血流が促進されることで、酸素や栄養素が効率よく各組織に運ばれ、新陳代謝の向上や疲労回復の助けにもなります。さらに、定期的に自転車を漕すことで血管の弾力性が維持され、高血圧の予防や循環器系の健康促進にも役立ちます。
関節への負担が少ない安全運動が可能
ペダルを漕ぐ動作は膝や腰、足首にかかる衝撃が少なく、ランニングやジャンプ系の運動と比べて関節を痛めにくい特徴があります。そのため、関節に不安がある人や高齢者、体重のある人でも無理なく取り組むことが可能です。さらに、自転車運動は負荷を調整しやすく、自分の体力や体調に合わせてペースや距離をコントロールできる点も魅力です。
基礎代謝の向上
ペダルを漕ぐことで下半身の大きな筋肉を使うため、筋肉量が増えやすく、筋肉の働きに伴って安静時のカロリー消費も高まります。これにより、日常生活でもエネルギーを効率的に消費でき、体重管理や脂肪燃焼のサポートにつながります。また、無理のない強度で継続して自転車を漕ぐことで、基礎代謝の向上が段階的に実感できる点も魅力です。
ストレス解消・リフレッシュ効果
ペダルを漕ぐリズミカルな動作は、心身をリラックスさせる作用があり、運動中に分泌されるエンドルフィンによって気分が軽くなる効果も期待できます。屋外でのサイクリングでは、自然や街並みの景色を楽しみながら運動できるため、気分転換やリフレッシュにも最適です。持久力アップ
ペダルを一定のリズムで長時間漕ぎ続けることで、心肺機能や筋肉の持久力が徐々に向上し、長時間の運動や日常の動作でも疲れにくい体作りが可能になります。また、有酸素運動として酸素の取り込み効率を高めることで、体全体の持久力を自然に引き上げる効果もあります。柔軟性の維持
ペダルを漕ぐ動作では、脚や股関節、足首の関節が一定の範囲で繰り返し動くため、関節の可動域を自然に保つことができます。日常生活ではあまり動かさない部位も適度に刺激されるため、関節や筋肉の柔軟性を維持しやすくなります。また、下半身の筋肉がほぐれることで血流も促進され、体のこわばりや疲れの軽減にもつながります。心の健康促進
ペダルを漕ぐリズミカルな動作は、ストレスを軽減するホルモンの分泌を促し、気分をリフレッシュさせる作用があります。さらに、屋外でのサイクリングは自然や景色を楽しむことができ、精神的なリラックス効果を高めることにもつながります。これにより、日常生活でのストレスや不安感が和らぎ、心の安定をサポートします。睡眠の質向上
適度な有酸素運動として体を動かすことで、体温やホルモンバランスが整い、夜間の深い睡眠を促進します。ペダルを漕ぐリズミカルな運動は、心身の緊張を和らげる作用もあり、寝つきがよくなるだけでなく、睡眠のサイクルを安定させる助けにもなります。体力の段階的向上
ペダルを漕ぐ動作は有酸素運動として心肺機能や筋力を徐々に鍛えることができ、無理なく体力を伸ばせる点が魅力です。負荷や距離、スピードを自分に合わせて調整できるため、運動習慣がない人でも少しずつ体力を高めることが可能です。バランス能力の向上
自転車に乗る際には、体の重心を一定に保ちつつペダルを漕ぐ必要があるため、自然と体幹や下半身の安定性が鍛えられます。これにより、立っている時や歩行時のバランス感覚も改善され、日常生活での転倒予防や動作の安定にもつながります。生活習慣病の予防
有酸素運動として心肺機能を高め、血流や代謝を改善することで、血圧や血糖値、コレステロール値の安定に役立ちます。下半身の筋肉を使うことで基礎代謝も上がり、肥満予防や糖代謝の改善にもつながるため、生活習慣病リスクを総合的に低減する効果が期待できます。自転車運動のやり方のコツ20選
自転車運動のやり方のコツを知っておくことで、効果的かつ安全に運動不足を解消できます。正しいフォームやペダルの漕ぎ方を理解すれば、下半身の筋力強化や心肺機能向上などの効果を最大限に引き出せます。また、無理なく継続できる習慣として取り入れやすく、関節への負担も抑えられるため、健康維持や生活習慣病予防にもつながります。
そこで自転車運動のやり方のコツについて解説します。
理想的なサドルの高さは、ペダルの一番下の位置で膝がわずかに曲がる程度です。このポジションを意識することで、下半身の筋力をバランスよく鍛えつつ、膝や腰への負担も最小限に抑えられます。さらに、正しい高さに設定することでペダルの回転がスムーズになり、心拍数や消費カロリーも安定します。
理想的なハンドルの高さは、肩や腕に力が入りすぎず、自然に背筋を伸ばした状態で握れる位置です。これにより、長時間の運動でも疲れにくく、ペダルを滑らかに回すことができます。また、正しいハンドルポジションは体全体のバランスを保ち、心拍数の安定や運動効果の向上にもつながります。
具体的には、足のかかとからつま先まで均等に力を伝え、ペダルを押し下げると同時に引き上げる動作も意識するとより効果的です。この動きにより、ペダリングがスムーズになり心拍数も安定して有酸素運動の効果が高まります。
具体的には、胸を軽く張り、肩の力を抜きながら自然に腕を曲げ、背骨を真っ直ぐに保つことを意識します。ハンドルの高さやサドルの位置も姿勢を安定させるポイントです。
具体的には、ハンドルを握る手の力を軽くし、肩を下げてリラックスした状態を意識します。背筋はまっすぐに保ちつつ、腕や肩の可動域を活かして自然にハンドルを操作することがポイントです。
理想的には、ペダルの回転に合わせて吸う・吐くを意識し、深くゆったりとした呼吸を心がけます。この呼吸法を取り入れることで、心肺機能の向上が促され、脂肪燃焼効果も高まります。また、呼吸が安定することで集中力が増し、長時間の運動でも疲れにくくなります。
理想的には、一定のスピードで滑らかにペダルを回し、無理のない範囲で漕ぎ続けることを意識します。一定のリズムを保つことで、筋肉に安定した負荷をかけられ、心肺機能の向上や脂肪燃焼効果がより効果的に得られます。
具体的には、ギアや抵抗を調整し、自分の体力に見合った強度でペダルを回すことがポイントです。運動中は心拍数を意識し、少し息が上がる程度の負荷を目安にすると良いでしょう。
休憩を挟むことで、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進させることが可能です。水分補給や軽いストレッチを取り入れることで、体内の疲労物質を排出し、次の運動に備えることができます。
補給のタイミングとしては、20~30分ごとを目安に、少量ずつ飲むことが効果的です。スポーツドリンクを活用すると、失われた電解質も同時に補えるため体調維持に役立ちます。
また、交通量の多い道路では歩行者や車両との距離を十分に保ち、予測不能な動きにも対応できるよう心がけましょう。
一方、運動後のクールダウンでは、ペダルをゆっくり回したり、軽いストレッチで筋肉を伸ばすことが重要です。
また、雨や強風の日には、防水性や風よけ機能のあるジャケットを着用し、安全面にも配慮することが必要です。反射材や明るい色の服を選ぶことで視認性を高め、交通事故のリスクを軽減できます。
また、集団走行ではスピード差やペース配分も意識する必要があります。一人一人の体力や技術に応じた位置取りを行うことで、無理な加速や減速を避け、体への負担を軽減できます。
加えて、手信号や声掛けなどのコミュニケーションを取りながら走ることで、集団内の意思疎通がスムーズになり、事故のリスクをさらに減らすことが可能です。
例えば、今週は10分長く漕ぐ、来週は少しペダルを速める、といった段階的な調整が理想です。
このように、自分の体の声をしっかりと感じ取り、その日のコンディションに合わせて運動時間を調整することで、無理なく継続することができます。
特に屋外でのサイクリングでは、風景や街並みの移り変わりを意識することで、体だけでなく心も活性化され、運動そのものを楽しむことにつながります。
特に運動不足を解消するために始めた自転車運動では、体調や筋力に応じて負荷を調整することが重要です。
また、リズムよく漕ぐことは心肺機能の向上や脂肪燃焼にもつながり、長時間の運動でも疲れにくくなります。無理に速度を上げるのではなく、自分の体力や筋力に合わせて一定のテンポを維持することが、運動効果を最大化するコツです。
そこで、曜日や時間をあらかじめ決めてルーティン化することで、無理なく続けやすくなります。短時間でも構わないので、決まったペースで継続することが、自転車運動を生活の一部に組み込むポイントです。習慣化することで、体力や基礎代謝の向上、ストレス解消、睡眠の質改善など、運動のメリットを安定的に享受できるようになります。継続は力なりという言葉の通り、定期的な運動が健康維持の鍵となります。
サドルの高さを自分の足に合った位置に調整する
ドルが低すぎると膝や腰に余計な負担がかかり、長時間の運動で痛みや疲労の原因となります。逆に高すぎるとペダルを漕ぐ際に足がしっかりと踏み込めず、効率よく筋肉を使えなくなります。理想的なサドルの高さは、ペダルの一番下の位置で膝がわずかに曲がる程度です。このポジションを意識することで、下半身の筋力をバランスよく鍛えつつ、膝や腰への負担も最小限に抑えられます。さらに、正しい高さに設定することでペダルの回転がスムーズになり、心拍数や消費カロリーも安定します。
ハンドルの高さを無理なく握れる位置に設定する
ハンドルが低すぎると前傾姿勢が強くなり、腰や肩、手首に余計な負担がかかります。逆に高すぎるとペダリングが非効率になり、下半身の筋力を十分に活かせなくなります。理想的なハンドルの高さは、肩や腕に力が入りすぎず、自然に背筋を伸ばした状態で握れる位置です。これにより、長時間の運動でも疲れにくく、ペダルを滑らかに回すことができます。また、正しいハンドルポジションは体全体のバランスを保ち、心拍数の安定や運動効果の向上にもつながります。
ペダルを回す際はつま先でなく足全体を使う
つま先だけで漕ぐと、ふくらはぎや膝に過度な負担がかかり、長時間の運動では疲労や痛みの原因になります。足全体を使ってペダルを回すことで、大腿四頭筋やハムストリング、臀部など下半身の大きな筋肉をバランスよく動員でき、効率的な筋力強化につながります。具体的には、足のかかとからつま先まで均等に力を伝え、ペダルを押し下げると同時に引き上げる動作も意識するとより効果的です。この動きにより、ペダリングがスムーズになり心拍数も安定して有酸素運動の効果が高まります。
背筋をまっすぐに保ち、猫背にならないよう意識する
前かがみの姿勢や背中が丸まった状態で漕ぐと、腰や肩、首に余計な負担がかかり、長時間の運動で疲労や痛みを感じやすくなります。正しい姿勢を維持することで、ペダルの力を効率よく下半身全体に伝えられ、筋肉への刺激も均等になります。具体的には、胸を軽く張り、肩の力を抜きながら自然に腕を曲げ、背骨を真っ直ぐに保つことを意識します。ハンドルの高さやサドルの位置も姿勢を安定させるポイントです。
肩の力を抜き、リラックスした姿勢で漕ぐ
肩や腕に力が入りすぎると、長時間の運動で肩こりや首の痛みを引き起こす原因となります。逆に肩の力を抜いて自然な状態を保つことで、上半身の余計な緊張が減り、ペダルへの力の伝達もスムーズになります。具体的には、ハンドルを握る手の力を軽くし、肩を下げてリラックスした状態を意識します。背筋はまっすぐに保ちつつ、腕や肩の可動域を活かして自然にハンドルを操作することがポイントです。
呼吸は止めず、自然なリズムで行う
息を止めて力任せに漕ぐと、心拍数が急上昇してしまい、短時間で疲労が溜まりやすくなります。逆に呼吸を意識してリズミカルに行うことで、酸素が全身に行き渡り、筋肉への負担も軽減されます。理想的には、ペダルの回転に合わせて吸う・吐くを意識し、深くゆったりとした呼吸を心がけます。この呼吸法を取り入れることで、心肺機能の向上が促され、脂肪燃焼効果も高まります。また、呼吸が安定することで集中力が増し、長時間の運動でも疲れにくくなります。
ペダルの回転は一定のリズムを保ち、急に速くしない
ペダルを急に速く回すと、筋肉や関節に無理な負荷がかかり、疲労や痛みを招くことがあります。また、リズムが乱れると呼吸や心拍数も不安定になり、有酸素運動としての効果が下がってしまいます。理想的には、一定のスピードで滑らかにペダルを回し、無理のない範囲で漕ぎ続けることを意識します。一定のリズムを保つことで、筋肉に安定した負荷をかけられ、心肺機能の向上や脂肪燃焼効果がより効果的に得られます。
適度な負荷をかけて心拍数を上げる
負荷が軽すぎると運動の効果が薄れ、逆に過度な負荷は筋肉や関節に負担をかけ、疲労や怪我の原因となります。適度な負荷を維持することで、効率よく心肺機能を鍛え、有酸素運動としての効果を高めることができます。具体的には、ギアや抵抗を調整し、自分の体力に見合った強度でペダルを回すことがポイントです。運動中は心拍数を意識し、少し息が上がる程度の負荷を目安にすると良いでしょう。
長時間漕ぐ場合は途中で休憩を挟む
連続して漕ぎ続けると筋肉や関節に負担がかかり、疲労や怪我のリスクが高まります。また、心拍数や呼吸も安定しにくくなり、効率的な有酸素運動ができなくなることがあります。休憩を挟むことで、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進させることが可能です。水分補給や軽いストレッチを取り入れることで、体内の疲労物質を排出し、次の運動に備えることができます。
水分補給を適宜行う
運動中は汗として体内の水分が失われるため、放置すると脱水症状や体力の低下、集中力の欠如を招くことがあります。特に夏場や長時間のライドでは、喉の渇きを感じる前に少しずつ水分を補給することが大切です。補給のタイミングとしては、20~30分ごとを目安に、少量ずつ飲むことが効果的です。スポーツドリンクを活用すると、失われた電解質も同時に補えるため体調維持に役立ちます。
路面や交通状況に注意し、安全第一で走る
道路の状態や天候によっては、滑りやすい箇所や段差、穴ぼこなどが存在し、思わぬ転倒や事故につながるリスクがあります。特に雨天や夜間の走行時には視界が制限されるため、速度を落として慎重に走ることが重要です。また、交通量の多い道路では歩行者や車両との距離を十分に保ち、予測不能な動きにも対応できるよう心がけましょう。
運動前に軽いウォームアップ、運動後にクールダウンを行う
ウォームアップでは、脚や腰回りの筋肉をほぐし、血流を促進することで、運動中のケガや筋肉の負担を軽減できます。軽いストレッチや足踏み運動を取り入れるだけでも、体がスムーズに動く状態を作ることが可能です。一方、運動後のクールダウンでは、ペダルをゆっくり回したり、軽いストレッチで筋肉を伸ばすことが重要です。
屋外では天候に応じて服装を調整する
気温や湿度、風の強さによって体感温度は大きく変わるため、薄手の速乾素材を重ね着して調整したり、寒い日には防風・保温性のあるウェアを選ぶことがポイントです。これにより、体温の急激な変化を防ぎ、快適な運動環境を保つことができます。また、雨や強風の日には、防水性や風よけ機能のあるジャケットを着用し、安全面にも配慮することが必要です。反射材や明るい色の服を選ぶことで視認性を高め、交通事故のリスクを軽減できます。
集団で走る場合は周囲との距離を意識する
前後や横のライダーとの距離が近すぎると、急なブレーキや進路変更で接触事故が起きやすくなります。そのため、走行中は常に前方の動きに注意を払い、互いの安全を確保できる十分なスペースを保つことが基本です。また、集団走行ではスピード差やペース配分も意識する必要があります。一人一人の体力や技術に応じた位置取りを行うことで、無理な加速や減速を避け、体への負担を軽減できます。
加えて、手信号や声掛けなどのコミュニケーションを取りながら走ることで、集団内の意思疎通がスムーズになり、事故のリスクをさらに減らすことが可能です。
定期的にスピードや距離を少しずつ増やす
一度に大幅に負荷を上げると、筋肉や関節に過度の負担がかかり、疲労やケガの原因になりかねません。まずは、自分の体力や体調に合わせて無理のない範囲で少しずつ変化を加えることが基本です。例えば、今週は10分長く漕ぐ、来週は少しペダルを速める、といった段階的な調整が理想です。
自分の体調や疲労度に応じて運動時間を調整する
疲れが残っているときに長時間漕ぐと、筋肉や関節に負担がかかり、思わぬケガや疲労の蓄積につながる可能性があります。逆に体調が良いときには、少し長めに漕ぐことで運動効果を高めることができます。このように、自分の体の声をしっかりと感じ取り、その日のコンディションに合わせて運動時間を調整することで、無理なく継続することができます。
音楽や景色などでモチベーションを保つ
お気に入りの音楽を聴きながら漕ぐと、リズムに合わせて自然にペダルを回すことができ、運動中の疲れを感じにくくなります。また、周囲の景色や季節の変化を楽しむことで、単調になりがちな運動も新鮮に感じられ、気分をリフレッシュすることができます。特に屋外でのサイクリングでは、風景や街並みの移り変わりを意識することで、体だけでなく心も活性化され、運動そのものを楽しむことにつながります。
無理せず、体に痛みや違和感があれば中止する
漕いでいる最中に腰や膝、肩などに痛みや違和感を感じた場合は、無理に続けるのではなく、すぐに中止する判断をすることが安全です。痛みを我慢して運動を続けると、怪我や慢性的な負担につながり、結果的に運動習慣を継続できなくなる可能性があります。特に運動不足を解消するために始めた自転車運動では、体調や筋力に応じて負荷を調整することが重要です。
ペダルを漕ぐ際はリズムよく、片足だけで力を入れすぎない
片足だけで力を入れすぎると、筋肉に偏った負荷がかかり、疲労や痛みの原因になりやすくなります。両足をバランスよく使い、一定のリズムでペダルを回すことで、下半身全体の筋肉を効率的に使うことが可能です。また、リズムよく漕ぐことは心肺機能の向上や脂肪燃焼にもつながり、長時間の運動でも疲れにくくなります。無理に速度を上げるのではなく、自分の体力や筋力に合わせて一定のテンポを維持することが、運動効果を最大化するコツです。
週に何度か定期的に行い、習慣化する
単発で行うだけでは心肺機能や筋力の向上、脂肪燃焼などの効果は持続しにくく、運動習慣として定着させることが難しくなります。そこで、曜日や時間をあらかじめ決めてルーティン化することで、無理なく続けやすくなります。短時間でも構わないので、決まったペースで継続することが、自転車運動を生活の一部に組み込むポイントです。習慣化することで、体力や基礎代謝の向上、ストレス解消、睡眠の質改善など、運動のメリットを安定的に享受できるようになります。継続は力なりという言葉の通り、定期的な運動が健康維持の鍵となります。
自転車のランキングをチェック
自転車を正しく選ぶには
サドルの高さ、
ハンドルの高さ、
フレームサイズ、
タイヤの太さ、
タイヤの種類(舗装用・オフロード用)、
ブレーキの種類(ディスクブレーキ・リムブレーキ)、
変速ギアの段数、
ペダルの種類(フラット・ビンディング)、
重量、
材質(アルミ・カーボン・スチール)、
サスペンションの有無、
ホイールのサイズ、
ブレーキレバーの握りやすさ、
シートポストの調整幅、
チェーンの種類、
ギアチェンジのスムーズさ、
フレーム形状(クロス・ロード・マウンテン)、
付属アクセサリー(ライト・泥よけ・スタンド)、
耐久性、
メンテナンスのしやすさ、
価格帯、
デザインやカラー、
乗り心地、
用途(通勤・通学・スポーツ・長距離)、
折りたたみ可否、
振動吸収性、
グリップの形状、
ペダルの回転の軽さ、
ブランドや評判、
保証やアフターサービス
を確認することが大切です。
口コミやランキングが充実しているショップがあるので、 是非あなたにピッタリの自転車を見つけてください。
■要チェック
口コミやランキングが充実しているショップがあるので、 是非あなたにピッタリの自転車を見つけてください。
■要チェック
まとめ
今回は
自転車の運動不足解消効果
についてのお話でした。
以上の説明がお役に立てたのであれば幸いですが、もし解決に至らないようであれば、 一流トレーナーの運動や食事指導が受けられるジムで 無料カウンセリング又は無料体験レッスンを受けてみてください。
■是非読んでほしい必読情報
以上の説明がお役に立てたのであれば幸いですが、もし解決に至らないようであれば、 一流トレーナーの運動や食事指導が受けられるジムで 無料カウンセリング又は無料体験レッスンを受けてみてください。
■是非読んでほしい必読情報